貸金庫の確認方法【貸金庫に遺言書が入ってた場合はどうする?】など相続手続きの流れ
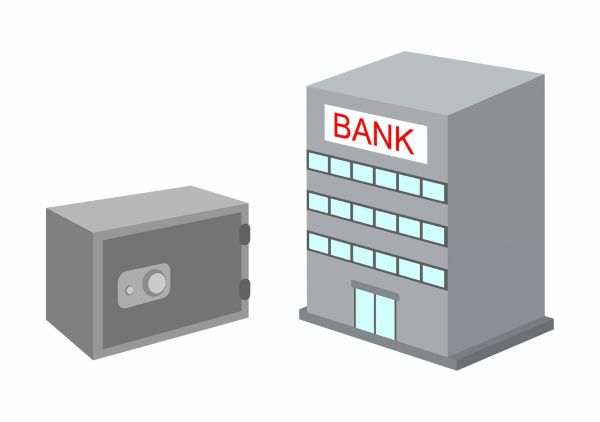
最近、金融機関の貸金庫を狙った窃盗事件が相次いで報道されています。特に、銀行や信用組合の元職員が関与するケースが続発し、利用者の不安も高まっています。
貸金庫は貴重品や重要書類を保管する場所として便利ですが、相続時には開け方や手続きに戸惑うことも少なくありません。特に、貸金庫の中に遺言書が保管されている可能性がある場合、適切な手順を踏まなければ開封できず、相続手続きが滞ることも。
本記事では、貸金庫の相続手続きの流れや、遺言書が見つかった場合の対応について詳しく解説します。
貸金庫の中身は相続税の対象?
貸金庫に入っている財産も、相続税の申告が必要です。亡くなった方(被相続人)の財産はすべて相続の対象となるため、貸金庫に保管されている現金や貴金属も例外ではありません。
「貸金庫に預けているから分からないのでは?」と思うかもしれませんが、税務署は被相続人の財産状況を調査する権限を持っています。金融機関にも照会が入るため、申告しなかった場合に発覚する可能性は十分にあります。適切に申告しなければ、ペナルティを受けることもあるため注意が必要です。
また、相続の対象はプラスの財産だけではありません。たとえば、貸金庫の使用料が未納になっていた場合、その未払い分もマイナスの財産として相続の対象になります。相続税の計算では、貸金庫の中身も含めて、すべての財産を正しく把握し、適切に申告することが大切です。
貸金庫を早く確認したほうがよい理由
貸金庫を放置してしまうと、後々面倒な手続きが発生する可能性があります。特に、遺言書が入っていた場合は相続の方法が変わるため、できるだけ早く中身を確認することが大切です。
遺言書があるかもしれない、どのような財産が入っているか分からない
貸金庫には、亡くなった方が生前に作成した遺言書が入っている可能性があります。遺言書がある場合、その内容に沿って相続手続きを行うことになります。しかし、遺言書を確認せずに相続を進めてしまうと、後から見つかった際に手続きをやり直さなければならないこともあります。
また、貸金庫には、預金通帳、株券、貴金属、実印などが保管されていることも多く、相続財産に関わる重要なものが含まれている可能性があります。こうした財産を見落とすと、相続税の計算や遺産分割協議に影響が出るため、早めに中身を確認することが大切です。
遺言書が入っていると思われる場合でも公正証書遺言の場合遺言書検索システムで検索し謄本の取得が可能
故人が公正証書遺言を作成していた場合、貸金庫を開ける前に、日本公証人連合会の遺言検索システムで確認できます。このシステムでは、全国の公証役場で作成された遺言の有無や保管場所を検索できます。
検索は、相続人や遺言執行者などの利害関係者が公証役場で申し込むことが可能です。必要な書類として、故人の死亡を証明する除籍謄本、相続人であることを示す戸籍謄本、本人確認書類などが求められます。検索手続きは無料ですが、公正証書遺言の謄本を請求する場合は、ページ1枚につき250円となります。
自筆証書遺言の場合・・・
自筆証書遺言が保管されている可能性がある場合は、故人が法務局の遺言書保管制度を利用していたかどうかを確認しましょう。この制度を利用していた場合、法務局で遺言書の原本を閲覧したり、証明書を発行してもらうことが可能です。
もし、遺言書保管制度を利用していなかった場合は、自宅や貸金庫を探す必要があります。遺言書は、タンスの引き出し、金庫、通帳や印鑑と一緒に保管されていることが多いため、これらの場所を重点的に確認するとよいでしょう。また、親族、病院、介護施設、顧問税理士や弁護士など、故人と関わりの深い人が遺言書の所在を知っている可能性もあるため、周囲にも確認してみることが大切です。
貸金庫には、相続に関わる重要な書類や財産が保管されていることが多いため、早めに中身を確認し、手続きを円滑に進めましょう。
貸金庫を開けるまでの流れ
故人が生前に貸金庫を契約していた場合、どこの金融機関にあるのか、どのような手続きが必要なのかが分からないことがあります。また、相続人全員の立ち会いが必要なケースもあり、スムーズに進めるには早めの確認が重要です。ここでは、貸金庫を開けるまでの手順を解説します。
貸金庫を契約している金融機関を調べる方法
故人がどこの金融機関で貸金庫を契約していたのか分からない場合は、まず以下の方法で特定を試みます。
1. 預金通帳の取引履歴を確認
貸金庫の利用料は、半年分または1年分が自動引き落としされることが一般的です。故人の主要な預金口座の入出金明細を確認し、「貸金庫利用料」の引き落とし記録を探します。
2. 遺品や郵便物を確認
金融機関からの「契約更新通知」や「利用明細書」が残されている場合があります。
3. スマホ・PCの履歴を確認
故人がオンラインバンキングを利用していた場合、金融機関の契約情報が見つかる可能性があります。
4. 金融機関へ問い合わせ
故人が取引していた可能性がある金融機関に、貸金庫の契約の有無を確認することもできます。ただし、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本や身分証明書)が必要となる場合があります。
金融機関での相続手続き
貸金庫のある金融機関が特定できたら、相続手続きを進めます。金融機関は、相続が発生すると故人の口座や貸金庫を凍結するため、すぐには開けることができません。開扉のためには、相続人全員の合意を得て、必要な書類を提出する必要があります。
一般的に必要となる書類は、以下のとおりです。
- 金融機関所定の申請書
- 相続人全員の同意書または遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または抄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 貸金庫の鍵またはカード(ある場合)
金融機関ごとに求められる書類が異なるため、事前に確認しましょう。
貸金庫を開ける方法
貸金庫を開けるには、基本的に相続人全員の立ち会いが必要です。
まずは契約先の金融機関を確認し、必要な書類を準備しましょう。手続きが複雑になりそうなら、金融機関や専門家に相談し、スムーズに進める方法を検討することが大切です。
1. 相続人全員が立ち会う場合
金融機関の指定した日時に相続人全員で訪問し、開扉手続きを行います。銀行の担当者が立ち会い、貸金庫内の財産が確認されます。
2. 代表者が開ける場合
金融機関によっては、相続人全員の書面による同意があれば代表者だけで開けられることがあります。同意書や委任状が必要なため、事前に準備しましょう。
全員の同意と立会いが難しい場合事実実験公正証書、遺言で指定された者(遺言執行者)が開ける
貸金庫の開扉には通常、相続人全員の同意と立ち会いが必要ですが、それが難しい場合には以下の方法が取られることがあります。
1. 事実実験公正証書を作成する場合
事実実験公正証書とは、公証人が自ら見聞きした事実を記録し、公正証書として作成するものです。これは、公証人が実際に体験した内容に基づいて作成されるため、高い証明力を持ち、裁判においても真正な証拠として扱われる公文書です。
貸金庫を開ける際に事実実験公正証書を作成することで、開扉の手続きや貸金庫の中に何が入っていたのかを公的に証明できます。具体的には、公証人が金融機関に立ち会い、いつ、どのような方法で貸金庫が開けられたのか、開扉の際の相続人の同席状況、そして貸金庫の中身がどのような状態だったのかを詳細に記録し、公正証書として残します。
この公正証書は、公証役場に原本が保存されるため、後々の紛争が発生した場合でも、貸金庫の中に何が入っていたか、誰がその場にいたかを客観的に証明することができます。
相続人の中に、貸金庫の開扉に反対する人がいる場合や、相続人全員の立ち会いが難しい場合、金融機関側が貸金庫の開扉に慎重な対応を取ることがあります。しかし、事実実験公正証書を作成することで、公証人が公式な記録を残すため、金融機関も手続きを進めやすくなり、相続人全員の同意が揃わなくても貸金庫を開けられるケースがあります。
また、貸金庫の中身が取り出された後に、相続人間で「財産が勝手に持ち去られた」「本当にその財産が入っていたのか」といったトラブルになる可能性もあります。しかし、事実実験公正証書を作成しておけば、開扉の状況や中身の詳細が記録されるため、こうした疑念を防ぐことができます。
2. 遺言執行者が開ける場合
故人が生前に作成した遺言書で「貸金庫の開扉に関する権限」を遺言執行者に委任していた場合、その人物が単独で貸金庫を開けることができます。遺言執行者が開扉するには、遺言書の正本または謄本、相続人の戸籍謄本、遺言執行者の身分証明書などが必要になります。
ただし、貸金庫内に遺言書が保管されている場合、事前にその内容を確認できないため、相続人全員の同意が必要となるケースもあります。
まとめ
貸金庫を開けるには、契約先の金融機関を特定し、相続手続きを進めることが必要です。その後、相続人全員の同意や立ち会いが求められますが、場合によっては事実実験公正証書の作成や遺言執行者の手続きによって開扉が可能になります。
相続人同士の調整が難しい場合や、開扉の手続きに不安がある場合は、公証人や弁護士に相談し、最適な手続きを検討することが重要です。貸金庫の中には、遺言書や重要な財産が含まれている可能性があるため、適切な方法で開ける準備を進めましょう。



